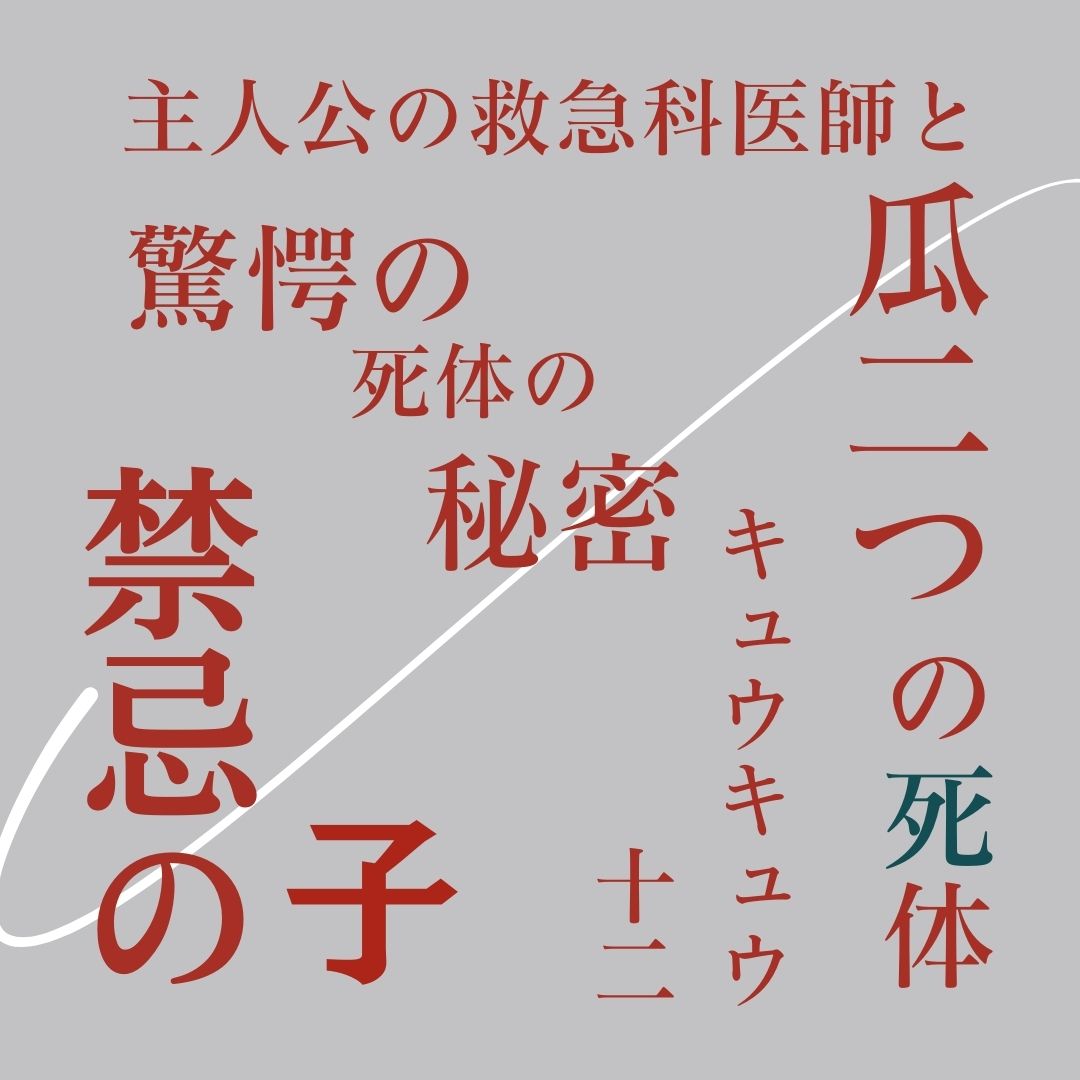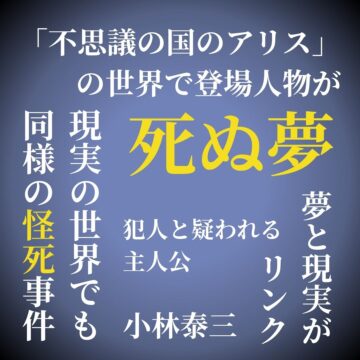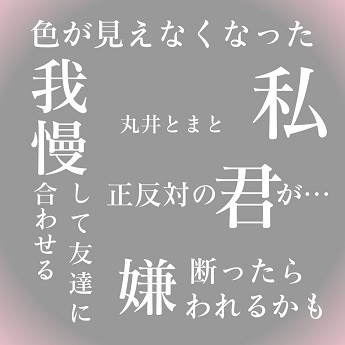@kengo_book この凄まじい結末は、まさに〝禁忌の子〟以外はあり得ないーー。 『禁忌の子』の紹介です📚 #本の紹介 #おすすめの本 #小説 #小説紹介

↑↑↑タップで詳細・注文へ↑↑↑
禁忌の子
- 著者名
- 山口未桜/著
- 出版社名
- 東京創元社
- 税込価格
- 1,870円
【スタッフのつぶやき】
●禁忌の子というタイトル時点で、私なら、タイトル見ただけでは決して手には取りません。
けんごさんの紹介のすごさですよ・・・
そして読み始めると、TVerで『あちこちオードリー』を見ようとしてたのに、そのまま止まらなくて最後まで読んでしまいました。本が動画に勝ったのは久しぶりでした。
ただ、後半は悲しかった。
この『禁忌の子』終盤で、吉野弘作の散文詩「I was born 」が出てきます。
「人間は生まれさせられるんだ。自分の意志ではないんだね」
先月、なだいなだ先生が「頼んでもないのに勝手にこの世界に産み落とされる」的な事を言ってたと書きましたが、今作では、色んな意味でそうであり、そうかも知れないと思って読み進めていたいくつも上を行く展開がありました。(まあ、私がミステリ初心者なのもあるかもしれませんが)
その上で、それでもなお苦しくても本人は生きていかなければならないし、生きていくべき物語が必要なんだと感じました。
自分たち本屋に照らし合わせると、多くの人に求められたからこそ書店は増えてきたはずです。誰だったか作家さんが、「戦後とにかく本に活字に飢えていた。文字であれば何でもよくて調味料のラベルでもよかった」と書いてました。なのに、今や書店はピークの半分。
人と企業は違いますが、「それでも生きていく」点は似ていて、「じゃあ」「でも」生きるには、過去ではなく今やこれからを考えるしかない。これからの需要・存在意義。手垢のついた言葉で言えばゼロサムではなくWin-Win。
①「死の水」を売る
アメリカで「リキッド・デス(Liquid Death)」という水が売れているそうです。
単なる水? そう、水デス(Liquid Death)。
(あ、本当にすみません)
特徴は
・ペットボトルではなくビール風アルミ缶入り(頭蓋骨のイラスト)
・コンサート会場やバーで売っている
・コンセプトは「ダサくない水」を売る
500mlで2ドル(約300円)。売上げは、年約400億円。
キッカケは、エナジードリンクの缶に水を入れて飲んでいるロックのミュージシャン等がいたことらしいです。お客側だと、酒は飲みたくないがペットボトルの水はカッコ悪いと思う人たちの需要に応えたと言えます。
水を売ってるんじゃない、ダサくないっていう記号を売ってるんだ。 (来たー!(意味不明))
これは、「iPhoneじゃないとイジメられるぅ」という子どもは分かるが、「そんなわけないでしょ、このAndroidください」という親は分からないかもしれません。でも需要に応える、インサイトを掘り起こすってのはそういうことかもしれません。
②売る努力不足
最近聞いた好きなエピソードに、小さな衣装パイプハンガーBOXの話があります。スチールパイプで枠組みがあってまわりをシートで覆ってありファスナーで開けるタイプの服を収納する背の高さ位のものです。それは単に小さめで収納量が少ないので売れなかったのですが、ミニマリストのお客様にたどり着いてから、ミニマリスト界で知れ渡り、売れるようになったそうです。
求めている人は実はいるのに、売る努力知らせる努力が足りなかったのだ、という言い方をしてました。(何かのYouTubeだった気がしますが、細かくは忘れました。)
今売れないから値下げするのはじり貧です。だからといって、目の前のお客様だけにそのままの価格では売れない。ましてや仕入れ値や原材料の高騰を理由に値上げなんてとても言えない。ココ壱番屋や長崎ちゃんぽんリンガーハットの値上げのように、お客様とお店のゼロサムゲームと取られて批判される場合もあります。でも、探せば、実は求めている人が見つかるんですね。
③シングルベッドが先に 売り切れてた頃
自分たちの実体験でも似たことがありました。
三洋堂書店では、夢グループのセールを月1回ほどやっています。ある月の商品にエアーベッドがありました。ダブルとシングルです。ダブルの方が価格の割に大きくてお得感があります。しかし、売り切れたのはシングルで、売切れ後もシングルの問い合わせが続きました。「シングルの方が大量に入荷でもしてりゃ ああ 辛くないのに」と思いつつ、スタッフの方に聞くと、「この辺は田舎だから、私なら来客用に臨時の布団として使いたいので大きくなくていいし、小さくたためるのが良い。」とのこと。私は勝手にフワフワ感を「売り」だと考えていましたが、少なくとも田舎であるこの地域の方の主目的に沿うのはシングルだったのです。大は小を兼ねる的な一般論ではなく求められる要素の解像度を高くすると売れるのだと実感しました。
今のままではダメ、というのは、逆に言えば改善すれば生き残れる。それは製品・プロダクトだけじゃなく、求められる人・場所を探して伝えることを含めて。自分事的にはそう解釈しました。
●先月の『アリス殺し』の感想
騙される気持ちよさを感じられた良い作品でした。多少グロい表現を除いては。
私はミステリ初級者なので、終盤「いやー、なるほど、そこかー・・・」と楽しめました。
あと『不思議の国のアリス』のあらすじと登場人物は把握しておくと、より楽しめます。(ネットを検索してあらすじを読んで、5本くらいアリスの紹介動画を見てから読みましたので、丁度良かったです)
ところで、ふしぎの国のアリスといえばディズニー。
ディズニーと言えば、今いろんな意味で話題の『白雪姫』。
そもそもの原点である1937年のアニメ版は、皆さんご覧になったことはありますか?
なんでも、初の長編カラー映画だったそうですが、実は当時かなり革新的だったそうです。
原画枚数が 25万枚(『崖の上のポニョ』でも 17万枚。AKIRAですら 15万枚だったそうです。)
もう、最初だから加減を知らないリソースのぶち込みっぷり。たまりません。
結果、「ヌルヌル動く」と言われる超絶滑らかな動きになったわけです。
その分、費用も半端なく170万ドル(現在だと3億ドル相当ともいわれます。約450億円)
ディズニーがつぶれるかもしれなかったし、失敗作だともささやかれたそうです。
しかし、その出来はすばらしく、世界にそしてその後何十年に渡って影響を与え続けたわけです。
今は、著作権が切れていて、三洋堂書店でも110円でDVDも売ってますので、この機会に是非手に取ってみてください。
それでですね。あの。110円なんですね。確かに紙のケースですし、広告宣伝費も掛かってないでしょうが。
それにしても110円とは。いいんですかね・・・?
(スタッフ:杜甫甫酒造)





 トップ
トップ