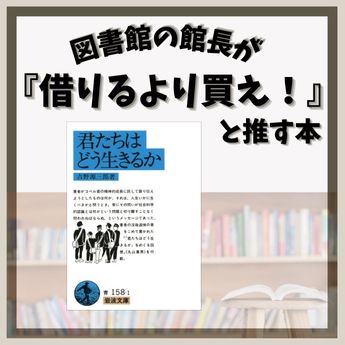
図書館館長なのに「借りるより買いたい本」を推すシリーズ vol. 26
日々10万冊を超える本に囲まれながら年間2,000冊以上読む図書館館長がどうしても手元におきたくて買ってしまう本とは?
「君たちはどう生きるか」
コペル君というあだ名の15歳の少年、本田潤一。成績は良いのに授業中もいたずらばかりしている。そのいたずらは人を困らせたり、嫌がらせたりするようなひねくれたものではなく、ただ人を笑わせて喜ぶ、いたって無邪気なもの。そんなコペル君の精神的成長の物語。
―――同名の大ヒット宮崎アニメとは異なるのでご注意を。
母子家庭のコペル君が抱く様々な疑問やものの見方について、物語の核である叔父さんがコペル君を導いていく。したためるノートブックの語りで、時には対話を通じて。
ある日ビルの屋上から人の群れを見下ろしながらコペル君が初めて感じた奇妙な気持ち。
「人間て、分子みたいなもの」
その言葉を聞いた叔父さんは、コペル君がものの見方を本気になって考えるようになったことを喜び、感動してノートブックにつづる。
コペルニクスの地動説を例えに、従来の手前勝手な考え方を転換して、異なる視点で色々な物事や人を理解していくことの大切さをコペル君に伝える。
広い世の中の一分子として自分自身を見たということは決して小さな発見ではないと賛辞する。
友人のうち1人が貧しい豆腐屋だとコペル君が初めて知ったとき、叔父さんは、世の中の大多数を占めているのは貧乏人であり、如何に裕福であることが「ありがたい」、「そうあることが難しい」かを教える。同時にまだ若いコペル君に消費専門家の分際で生産する人を見下し馬鹿にしてはならないと説く。
ある雪の日、友人4人と固く助けあう誓いをしていたにもかかわらず、上級生に絡まれ他の3人が殴られても、自分だけが怯えて傍観してしまったコペル君。卑怯者だと自責の念に駆られて塞ぎ込んでしまう。
叔父さんは、素直に自分の過ちを認めて許しを請う気持ちを正直に友人に伝えることを助言する。たとえ結果がどうなろうとも。
書かれたのは1937年。どのような時代であれ、青少年期であれ、家庭、学校、会社などどうであれ、常に「君たちはどう生きるか」なのだ。
また、環境破壊、AI、パンデミック等々地球規模の未曾有の事態にある現代だからこそ、改めて同書を読む意義がある。
ところで、今、君たちはどう生きていますか。
「君たちはどう生きるか」はこちら

↑↑↑タップで詳細・注文へ↑↑↑
君たちはどう生きるか
- 著者名
- 吉野源三郎/著
- 出版社名
- 岩波書店
- 税込価格
- 1,067円





 トップ
トップ

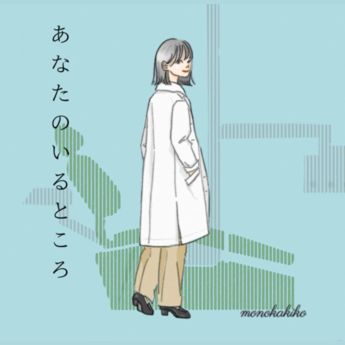
_12月コミック新刊案内.jpg)