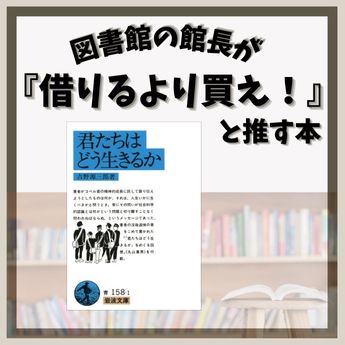(二)
いま診療室にほかの患者がいないことに、菫は感謝した。
四つある診療台はそれぞれ衝立で仕切られてはいるけれど、個室というわけではない。衝立を隔てた隣の声は、筒抜けである。
だからこそ、個人情報のやりとりはなるべく口頭ではしないように普段から気をつけているし、スタッフにも注意している。けれど、いまはどうしても、訊かないわけにはいかなかった。
「遠野さん、お聞きしたいことがあるのですが……」
「はい」
遠野が横になったまま、細い目を薄く開いて、菫を見あげる。
「失礼ですけど、近くにお住まいではありませんよね」
問診票に記載されていた住所は、愛知県名古屋市になっていた。
平川歯科医院は、ネットの評価が特別いいというわけでもない(そして医者は怖いと言われている)、小さな町医者だ。最寄り駅までは徒歩患者は徒歩十五分かかる。よって、患者のほとんどは地元民で占められる。県外からの受診はかなり稀なことだった。
「ああ、はい。出張先で、突然歯が痛みだして。スマホで近くの歯医者を検索したら、ここが出てきたもので。でも、予約もなしに来たから迷惑でしたかね」
遠野は苦笑しながら答えた。
「いえ、迷惑というわけでは」
菫はそう言って、保険証が使えないため今日の治療費は全額自己負担になること、住んでいる地域の役場に期限内に申請すれば払い戻してもらえることを説明した。
「では、診させてもらいます。滝沢さん、歯式をお願い」
「はい」
菫が歯式記号を読み上げ、日向子が素早くカルテに記入していく。
歯列記号とは、患者の口腔内を上顎、下顎、左右の歯を1番から8番に分け、それぞれの位置や状態を記録するための重要な情報だ。
日向子が記録を終えたのを確認して、短針で奥から歯を軽くコツコツと叩く。
「ここは響きますか」
「うーん……?」
「隣はどうですか」
「そこは少し痛むかな」
右下顎第二大臼歯の溝の部分が窪んで、茶色く変色していた。
「右下の奥が虫歯になっていますね。エナメル質まで到達しているので、少し削って詰め物をする必要があります。それと、全体的にタバコによる変色が目立ちます。この程度なら毎日の歯磨きで防げるでしょう」
「ああ、たまに夜疲れててそのまま寝ちゃったりするから……」
遠野は気まずそうに言って、ふっと口を緩ませた。
「なんだか、学校の先生に怒られてるみたいだな」
その言葉に、菫ははっとした。
自分はただ、注意事項や、患者にとって必要だと思うことを伝えているつもりだった。
しかし患者からすれば、虫歯の治療に来たのにほかの汚れまで口を出されたら、いい気がしないだろう。
こういう治療に関係ないことをわざわざ口にするから、
“怒られてるみたい”
“言い方がきつい”
などと言われるのだ。
「失礼しました。余計なことを」
「いや。はっきり言ってくれたほうが誠実な感じがして安心しますよ」」
垂れ目がちの遠野の目がさらにふにゃりと緩んで、柔らかい表情になる。
名前も顔も知らないはずなのに。自分にはとてもできないその自然な表情を、菫はやはり知っている気がした。
ユニットの横についているスイッチを押して、背もたれを起こす。
「今後の治療のためにレントゲン写真を撮っておいたいいと思いますが、どうされますか」
自己負担だと七千円弱かかると伝えると、遠野は首を振った。
「あわてて駆け込んだから、そんなに持ち合わせがなくてね。レントゲンは近くの歯医者で撮ってもらうよ」
クレジットカードも対応していると、年配の患者にも見えるよう受付の目立つところに書いてあるはずだ。それでも断るのは、役所に申請するのが面倒だからだろう。手続きのわずらわしさから申請をしない患者はけっこう多い。
「わかりました。では、消毒をしてお薬を塗っておきます」
患部に照射し、炎症を抑える薬を塗って、今日の処置は終わった。治療の続きは家の近くの歯医者でするという。
「お大事にしてください」
日向子が笑顔で見送り、菫に声をかけた。
「菫先生、難しい顔してますけど、大丈夫ですか?」
「ええ……」
改めて考えてみても、やはり妙だった。
彼はたしかに虫歯を患っていたけれど、神経のある歯髄までは達するほど深くはなかった。歯肉の炎症も起こしていない。つまり、軽症と言っていいレベルだった。
わざわざ県外の歯医者に駆け込まなければならないような、耐えられないほどの痛みではなかったはずだ。
それなのに遠野は、保険が使えないとわかっていて、わざわざこの小さな歯科医院にやってきたのだ。それも午後一番、一日の中でいちばん時間に余裕がある時間に。
彼の言葉を信じるなら『近くの歯医者をスマホで検索したらここが出てきた』ことになるけれど……。
菫にはその奇妙な行動が、わざと歯医者に来る理由を作ったような気がしてならなかった。
でも、どうしてそんなことをする必要があるのだろう。
院長室に戻り、遠野のカルテを見直す。うっすらとヤニ汚れはあるものの、全体的にはきれいな歯だと思った。汚れが目立つのは、ほかに欠けている部分が少ないからだ。目立った虫歯は右下顎第二大臼歯だけで、ほかに詰め物や被せ物はなかった。左右の上顎第三大臼歯(親知らず)が二本残っており、隣の歯を少し圧迫している。
菫は机の棚からノートを取り出し、口腔内の様子を細かく書き出した。写真が撮れないのなら、手書きで残しておくしかない。
とくに既視感を覚えたのは、中切歯と側切歯(前歯四本)、そしてその脇にある犬歯だった。この六本は比較的虫歯になりにくく、噛み締めによるすり減りも少ないため、形が変わりにくい歯といえる。
似ている、と思った。一つ一つの歯の大きさ、隙間や歯槽の位置。そして夫も遠野と同じで、上顎の親知らずが左右二本、残っていた。
しかし、似ていると思っただけで、同じかどうかは判断できなかった。人の口腔内は年齢とともに変わっていくからだ。レントゲン写真があればもう少し正確に判断できたかもしれないが、手書きの情報だけでは心もとない。
アレを確認しなければ——。
「先生、白石さんがいらっしゃいました」
扉の外から声がする。
「すぐに行くわ」
返事をして立ち上がる。
まさか、十五年前にいなくなった夫が戻ってきた——なんてことが、あるだろうか。
『遠野慎一郎』
顔も名前も違うのに夫と同じ歯をもっているあの男は、いったい何者なのか。
わだかまりは大きくなるばかりだったが、診療室に入った瞬間に、切り替えた。
仕事が終わるまでは、ひとまずあの男のことは忘れていよう。
そうしなければ、頭がおかしくなりそうだった。
「お先に失礼しまーす」
着替えを終えたスタッフたちが挨拶をして帰っていく。
「菫先生、まだ残っていかれますか?」
院長室でパソコンに向かっていると、施錠係の岩沼が顔をのぞかせた。
岩沼は勤続年数三十二年のベテラン歯科衛生士だ。鍵の管理から点数表(診療報酬を請求するためのリスト)のチェックまで、色々と任せている頼りになる存在だ。
「ええ、鍵は閉めておくので。お疲れさま」
「はーい、お疲れさまです」
岩沼が帰ってから、菫はパソコンに入っているファイルを探した。
夫である平川良平の、カルテのデータだ。
カルテの保存期間は一般的に「治療が完結した日から五年間」と法律で定められている。しかし近年は、医療事故による損害賠償請求の消滅時効が二十年となっているため、長期の保存が望ましいという声が増えている。実際、医療機関によっては二十年間、もしくはそれ以上の長期保存を独自に定めているところもある。
平川歯科医院はそんな特例が認められるような病院ではないので、五年が経過したら業者に依頼して、すべて処分するよう言われている。
そして当然のように、すべて紙カルテである。災害時のデータ紛失などを防ぐためにも電子カルテに切り替えたほうがいいと何度か言っているのだけれど、院長である義父はまるで聞き耳持たず。副院長である義母は、基本的に院長の意見には反対しない。
よって、五年より前の診療記録は、どこにも残っていないことになる。
一人の患者——良平のカルテのデータ以外は。
紙カルテのデータは十年前、ほかの患者のカルテと一緒に処分しているけれど、データだけは自分のパソコンの中に残しておいたのだった。
診療記録やレントゲン写真。良平がいつか帰ってきたとき、もしかしたら役に立つかもしれないと思った。
「え……」
菫は愕然としてパソコンの画面を見つめた。
どこを探しても、ファイルは見つからなかった。
わざわざ残しておいたデータを自分で消すはずはない。
だったら、誰かが消したということになる。
ファイルには鍵をかけていたから、そんなに簡単に開けるはずはないのに。
いったい誰が……?
考えたくないけれど、いちばん可能性があるのは、院長でも副院長でもほかのスタッフでもなく、良平だった。
良平は医院のスタッフではないけれど、医療機器のメンテナンスなど、仕事でたびたび出入りしていた。さらに定期検診で、患者としても来院していた。良平がいることで不審に思う人間は誰もいなかったのだ。
当時は菫専用の部屋はなく、カウンターの奥にパソコンを置いていた。つまりパスワードさえ突破すれば、関係者なら誰でも触ることができたのだ。
もっと用心しておくべきだった。若かったから、なんていうのは言い訳にもならない。
わかるのは、誰かが、何か目的があって、データを消したということだった。
診療記録を消したい人物がいるとしたら——それはやっぱり、本人しかいないのではないだろうか。
でも、どうしてそんなことをする必要があったのか、わからなかった。
ふと思いついて、受付のカウンターに行った。入口の扉の上に一つ、監視カメラが取り付けられている。そこに保存された六時間前の映像を、巻き戻して見てみた。
午後一時半に、ワイシャツ姿の男性かやってきた。
突然痛みを覚えてあわてて近くの歯医者に駆け込んだなんていう様子はどこにもない、ゆったりとした足取りで、遠野は扉を開けて入ってきた。
小さな画面の、荒い白黒映像に映っている男の姿を、菫は何度も繰り返し眺めた。
見れば見るほど、そこにいるのが誰なのかわからなくなった。





 トップ
トップ