【熱田図書館コラムVol.21】人としての一線を問う~満州から故郷・諏訪までの壮絶な生きるための記録(ノンフィクション)~「流れる星は生きている」を推す
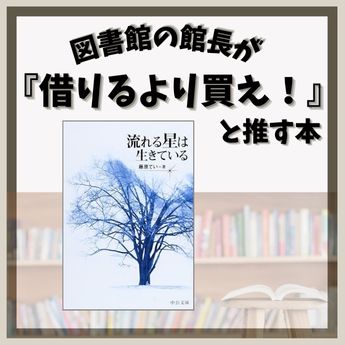
図書館館長なのに「借りるより買いたい本」を推すシリーズ vol. 21
日々10万冊を超える本に囲まれながら年間2,000冊以上読む図書館館長がどうしても手元におきたくて買ってしまう本とは?
「流れる星は生きている」
人生には読まなければならない本がある。
好きとか嫌いとかではなく。現代日本人が忘れかけている、或いは他人事ととらえている―――“戦争”について。
「流れる星は生きている」は第2次世界大戦が終わる間際、昭和20年8月9日、満州新京から3人の子供を連れて日本へ辿り着くまでの筆舌し難い壮絶な記録である。
昭和18年、夫(後に作家となる新田次郎)が満州に赴任することになり、愛児とともに新京(現在の長春)に渡った藤原てい。
満州での暮らしは順調だった。
だが平穏は突然破られる。それは末っ子の咲子が生まれて1か月たった晩だ。夫が非常招集され、6歳の正弘、3歳の正彦、咲子と自分だけで新京から脱出しなければならなくなった。
その町に暮らしていた仲間であった日本人たちとともに。
本を読み進めるうちに、人間の本性とはこうも醜いものなのかと思い知らされる。
3児を抱える母に食料を分け与える者はいない。
水筒に水を汲もうとしても屈強な男たちに先を越されて飲み水にさえありつけない。井戸端でおむつを洗おうとしても、汚いことをするなと怒鳴られる。
一方で鍋に入れた水で顔を洗う者たち。
てい親子が水も汲めない状況にもかかわらず。ろくな食べ物もなく、下痢が酷くなって衰弱していく子供。
その脇で缶詰や砂糖、お粥やスープを楽しそうに食べる人たち。
仲間だった同胞から受ける惨い仕打ち。子供の下痢が臭いと罵倒される。何の助けもない。人としてあるべき温情や優しさの欠片すらない。
逃亡の日々は真夏から真冬へ。
便所の汚物さえ凍りつく。人が飢えや寒さや感染症で死んでいく。親が子を殺す。気がふれる者。自殺する者。
ジフテリヤに罹患する正弘。高額な血清を打たなければ助からない。
馬糞がうず高く積もった貨車での移動。そして38度線を越えるため歩いて山越え。足の裏には無数の小石や何かの破片が刺さる。死に物狂いで親子は行進をつづける。
日本の港に着いてさえなお他人を騙して金品を巻き上げようとする同胞たち。敗戦で混乱状態の日本。親子は無事故郷へ辿りつけるのか祈るように読む。
―――心優しい善人であっては生き抜けない。優しさと脆弱さをはきちがえてはならない。
それは現代でも同じだ。本を読む気力さえ無い困難な状況にある人にこそ、「流れる星は生きている」を読んでいただきたい。続編「旅路」もあわせて是非。
「流れる星は生きている」はこちら

↑↑↑タップで詳細・注文へ↑↑↑
流れる星は生きている
- 著者名
- 藤原てい/著
- 出版社名
- 中央公論新社
- 税込価格
- 880円
熱田図書館長 佐々木
5歳で角膜移植した際、ドクターからの「喫煙禁止」と「読書禁止!」との言葉を忠実に守り続けるも、なぜか現在図書館長。
趣味は合気道、英語学習、旅行、温泉、アニメ、韓流、カラオケ、SNS、読書?
その他テニス、スキューバ、サーフィン、水泳・・・多趣味でキリがありません。
今現在の推しアイドルは、「ILLIT」! かつては「少女時代」。
アフタヌーンティーは日本、英国など有名店を制覇中。
こだわりはスコーン。
文中で登場した作品たち

↑↑↑タップで詳細・注文へ↑↑↑
旅路
- 著者名
- 藤原てい/著
- 出版社名
- 中央公論社
- 税込価格
- 880円





 トップ
トップ


