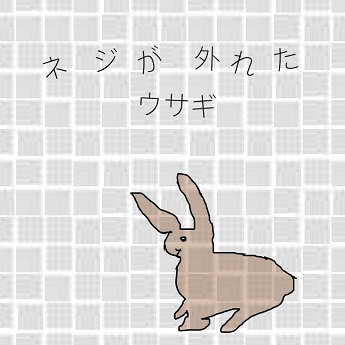(四)
今日、『喫茶ネリネ』は臨時休業だ。
小野寺かおるはいつもよりゆっくり朝の支度を済ませると、店から徒歩十五分ほどの場所にある中学校に向かった。
門の前で楽しそうに盛り上がるグループに顔見知りを見つけて会釈をする。かおるの息子、律の同級生の母親だ。
かおるは仕事柄顔が広いと思われがちだが、ママ友の集まりにはめったに参加しないので、気軽に声をかけられる相手はほとんどいない。別に無理して話す必要はないのだが、授業参観など校内での行事のときには困ってしまう。かおるは極度の方向オンチなのだ。
もう何度もこの学校に来ているのに、いっこうに教室の配置を覚えられない。いい加減覚えろよな、と最近生意気になってきた息子にまで呆れられる始末だ。
――だって、広すぎるのよ、この学校。
昇降口に向かう途中、教室の窓から顔を出しておーいと誰かを呼んでいる男子生徒がいた。見上げて、かおるは思わず顔をほころばせた。律が、満面の笑みで手を振っている。どうせまた迷うだろうからと、わざわざ教えてくれているのだ。
律のやわらかい猫っ気が、風になびいてふわふわと揺れる。
かおるも笑顔で手を振り返した。
「小野寺さん、小野寺さん」
下駄箱で靴を履き替えていると、後ろから声をかけられた。さっき門の前でおしゃべりをしていた母親だった。
「久しぶり。小野寺さん、相変らずお若いわねえ」
「原田さんこそ」
かおるはにっこりとほほ笑む。わざわざ追いかけてくるなんて、よっぽど話したいことがあるのだろう。
何かは、聞かなくても想像がつく。
「ねえ聞いた? 南ちゃん、いじめられてたんですって。かわいそうよねえ」
「そうなの」
かおるは初めて聞いたような素振りをする。
喫茶店では、さまざまな話題が飛び交う。ちょっとした世間話や人前では話しにくい内緒話でさえ、つい話したくなってしまう。大げさかもしれないが、それが喫茶店という場所の魔力だ、とかおるは思っている。
だからこそ、店で耳にした話は絶対に外で話さないと決めていた。
「でね、学校側は必死に隠したがってるみたいなの。ねえ、ひどいと思わない?」
そこまで知っているなら、かおるに聞くこともないだろうに。いや、誰でもいいからしゃべりたいだけなのだろう。言いづらい噂ほど、広まるのは早いのだ。
「そう……でも、私はあまりその子のことを知らないからなんとも」
やんわりと言いながら、靴を脱いでスリッパに履き替えた。一気に白けた空気になったが、構わなかった。
こういう噂話に気軽に乗れないから、友達ができないのだろうか。そうだとしても、亡くなった子の噂をあることないこと触れ回ることで成り立つような関係なら、やっぱりいらないと思う。
授業は数学だった。男性教師が証明の問題を黒板に書き、生徒が手を挙げて答える。窓際に座る律も手を挙げかけたが、自信がないのかすぐに引っ込めてしまった。窓からぶんぶん手を振る元気はあるのに、こういうところでは引っ込み思案なのだ。そういうところはかおるにそっくりだった。
かおるの学生時代は勉強漬けの日々だった。部活や学校帰りの寄り道など、青春らしいことをした記憶がない。成績は学年トップが常で、名門大学への進学を期待されていた。
かおるの父親は医者だった。人と話すのは苦手だったが、父親の仕事に憧れ、いつかは自分も医者になって人を助けるのだと思っていた。
しかしかおるが高校三年生のとき、その夢はある事件によって、粉々に砕かれたのだった。
かおるは大学には進学しなかった。それどころか、三年生の後半はほとんど登校すらできなかった。
何を目指せばいいのか、わからなくなってしまったのだ。
かおるは目を閉じて、深呼吸をしてから、ふたたび目を開けた。
しっかりしないと。今日は律を見るためにここにいるのだから。
律を見ると、かおるのほうを心配そうに伺っている。律は人の心に敏感で、些細な表情の変化にもよく気づく。
――ああ、息子にまで心配させてしまっている。授業中に息子に心配される母親って、どうなの。
学校という独特な空気に触れると、たまに当時のことがフラッシュバックする。
授業の終わりを告げるチャイムが鳴る頃には、どっと疲れていた。
ハーブティーが飲みたい、と思った。
体育館って、どこだっけ。
今日の授業は午前中だけで、参観の後は体育館に集まって子供と一緒に帰ることになっていた。ほかの人についていけばいいだろうと安易に考えていたが、ちょっとトイレに寄っているうちに、廊下には誰もいなくなっていた。
仕方なく当てずっぽうで向かった先は理科室で、かおるは肩を落とした。
この方向オンチ、どうにかならないものだろうか。今さらどうにもならないのはわかっているけれど。
ふと、『保健室』というプレートが目に留まった。
ようやく救いの手を見つけた気分だった。
保健室なら、きっと早苗先生がいるはずだ。いや、いてくれないと困ってしまう。
かおるが扉に手をかけたとき、ガラリと向こうから開いた。
出てきたのは早苗先生ではなく、小柄な女子生徒だった。
人がいるとは思わなかったのだろう。目をパチパチさせてかおるを見ている。
「あっ、ごめんね。あの、体育館ってどう行けばいいのかな? 迷っちゃって」
「体育館はあっちですけど……」
女子生徒は、おずおずと向かいの校舎を指した。
見ず知らずの中学生に助けを求めている自分にさらに情けなさが増しつつ、お礼を言って早足で体育館に向かった。
「お待たせ!」
体育館に着くころにはほとんどの生徒がすでに帰っていた。
「遅っ。またどっかで迷ってたんだろ」
かおるの顔を見るなり律がむくれて言う。
「ごめん、ごめん」
「ま、いつものことだし別にいいけど」
と律が言って、すたすたと先を歩く。
「律」
学校から少し離れたところで、気になっていたことを尋ねた。
「冴島南さんって女の子、知ってる?」
事故から一か月が経っていた。親子の会話で、その少女のことを話したのは初めてだった。
「知ってるけど、よく知らない。違うクラスだし、ほとんど話したことなかったから」
話したことなかった――たぶん、無意識なのだろう。さりげなく口にされる過去形に胸が痛んだ。
「一年の途中から、ほとんど教室来てなかったっていうのは聞いた」
「そう……」
その話を聞いたときから、ずっと気になっていた。
早苗先生はあのとき、何か大事なことを伏せて話しているように思えたから。
それが何かは、かおるにはわからなかったけれど。
――明るくて、優秀で、何の問題もなさそうな子。
――いじめられてたんですって。かわいそうよねえ。
二人の声を反芻する。
大人の前では、見せなかった。いや、きっと、見せられなかった。
少女の本音が聞きたかった。
お節介なのはわかっている。会ったこともない他人が無闇に首を突っ込むような軽い問題ではないことも。
でも、あの場所なら……『喫茶ネリネ』なら、それが叶うかもしれない。
かおるが一方的にそう思っていてもだめなのだ。
お互いが強く“会いたい”と思っていなければ。
家族や、友達や、先生。
南のことを大切に思っていた誰か。
南も同じように大切に思っていた誰か。
きっと、どこかにいるはずだから。
その誰かを、引き合わせたいと思った。
それが叶うのなら、お節介と言われようと構わない。
「冴島さんのことはよく知らないけど……仲いい友達がいたのは知ってる」
律がポツリとこぼした。
かおるはえっ、と驚いて律の顔を見た。
「あいつなら、もしかしたら会えるかもしんない。母さんの店で」
律はぽつぽつと話しはじめた。
彼女の名前は、森田若菜。律は小学校のとき同じクラスで、何度か公園や学校で一緒に遊んだこともあるという。
かおるは名前を聞いてもわからなかった。子供の同級生でも、異性となるとわからない子はけっこう多い。
もともと大人しいタイプで、あまり積極的に話すほうではなかった。中学ではクラスも別々になり、顔を合わせることもほとんどなかった。
しかしあるとき、若菜が一年生の一学期から突然教室に来なくなったと友達に聞いて、何があったのかなと、少し心配になった
若菜は毎日保健室にいるという。いちおう学校には来ているらしい。気になってはいたけれど、わざわざ保健室に見に行くのは冷やかしみたいで気が引けた。そして気になりつつ何もできないまま、二学期になってしまった。
たまたま体育の授業でサッカーボールを顔面に受けて鼻血を出し、それを理由に保健室を覗いてみたことがあった。
そこに若菜と、もう一人、南がいた。ベッドを囲う水色のカーテンが少しだけ開いていて、すき間から楽しそうに笑い合う二人の姿が見えた。
「なんか、楽しそうだったんだ」
律はそう言いながら、唇を噛んだ。
「なんだ、友達いるんじゃん、て思ったんだ。でも、話くらい聞いとけばよかった」
律は、声を震わせて泣いていた。かおるも泣いた。
律の気持ちが、かおるには痛いほどわかった。
あのとき、声をかけていたら、未来は違ったかもしれない。
そんな大それたことはできなかったかもしれないけれど、もしかしたら、状況を少しでも変えることができていたら、南は死ななくてよかったかもしれない。
かおるにとって南は、たとえ会ったことがなくても、知らない女の子ではなくなっていた。
たぶん、早苗先生の話を聞いた時から。
「わたし、その若菜っていう女の子にさっき会ったと思う」
「え、そうなの」
「その子、探してくるから律は先に帰ってて」
「ええっ、ちょっと!」
律が慌てて呼び止めた。
「俺、森田のうち知ってるよ」
息子が救世主に思えた。
「つうか、ふつうにもう家帰ってんじゃないの」
「そうだよねえ」
「考えなしかよ……」
若菜の家の前まで来てみたものの、家の周りに人の気配はなく、車も停まっていない。
かと言って、いきなりチャイムを押して尋ねるのも不審に思われるのではないか。
いやいや。子供同士は同級生なわけだし……。
と、そのとき、前のほうから小柄な少女が歩いてくるのが見えた。
「あ」
律が言った。
かおるも、さっき保健室で会った女の子だと気づく。
ほかの生徒たちが親と一緒に帰る中、この子は一人で帰ってきたのか。
そして、おそらくほかの生徒たちになるべく会わないよう、回り道をして帰ってきたのだろう。
若菜が顔を上げてこちらに気づき、ピタリと足を止めた。
「森田さん。こんにちは」
かおるは歩み寄って、にっこりとほほ笑んだ。
「えっ、はい」
若菜は言いながら、一歩後ずさる。
あきらかに怪しまれている。というか、怯えられている。
でも、今は遠慮するときじゃない。
かおるは鞄の中から、一枚の長方形のカードを取り出した。店名と住所と電話番号が書いてある、シンプルな名刺だ。
「わたし、小野寺律の母で、この近くにある『喫茶ネリネ』という喫茶店の店主をしている小野寺かおるといいます」
「いきなり営業かよ」
律が隣で呆れ顔をする。
「まずは名乗らないと失礼でしょう」
「あの、うちに何か……」
「おい、森田さん、困ってんじゃん」
「律はちょっと黙っててくれる?」
と言うと、律はおとなしく口をつぐんだ。
若菜は名刺を受け取って珍しそうに眺めている。
たしかに律の言う通り、大人しそうな子だった。でも、口や表情に出さなくても、心の中に溜め込んだ気持ちが、きっとたくさんあるはずだ。
「もしね、誰にも言えずに悩んでいることがあったら、ここに来て。絶対に誰にも言わないって約束するから」
かおるの言葉に、若菜ははっと目を見開いた。
その反応に、かおるは確信した。
やっぱり――この子は、誰かに秘密を話したがっている。
それなら、自分にできることは一つだけだ。
「おいしいハーブティーを用意してお待ちしています」
かおるはそう言って、にっこりとほほ笑んだ。





 トップ
トップ