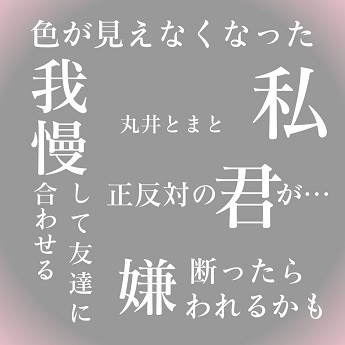(二)
事情はよくわからないけれど、一日待っているなんて、なかなか気合いが入っている。
横目でおばあさんの様子を伺うと、メニュー表を近づけたり遠ざけたり首をひねったりしながら、何を頼もうか悩んでいるようだった。
「よろしければ、わたしから説明させていただきます」
かおるさんが言うと、おばあさんが安心したように顔をほころばせた。
「そう? じゃあ、お願いしようかしら」
「かしこまりました」
かおるさんは歌うように朗々と、ハーブティーの説明を始める。
「当店では、その日の気分や体調に合わせてお選びいただけるブレンドハーブティーが人気です。
イライラするときはリラックス効果のあるネトル、レモングラス、カモミール、ラベンダーのブレンドが効果的です。
冷えが気になる方には、こちらのレモングラス、ローズマリー、ジンジャーのブレンドがおすすめです」
おばあさんは、色々あって迷っちゃうわねえ、と首をかしげた。
「それより、外が暑くって。何か、甘くて冷たいのが欲しいわ。まだ四月だし、かき氷なんてないわよねえ」
「それなら、コーディアルはいかがでしょう」
「なあに、それ」
おばあさんが目を瞬かせた。舞も初めて聞く名前だった。
「コーディアルというのは、ハーブや季節の果物をシロップ状に凝縮したお飲み物です。とっても甘くておいしいですよ」
「あらおいしそう。それをいただこうかしら」
「かしこまりました」
かおるさんは小さくおじぎをして、カウンターの奥に戻ると、棚に並んだ瓶をいくつか手に取った。
静かな店内に、カチャカチャとガラスの音が響く。
手元はカウンターの壁で見えないが、ハーブのいい香りがこちらまで漂ってくる。
先に、舞のハーブティーが運ばれてきた。
「お待たせしました。こちらネトル、マルベリー、リンデン、ヒースのブレンドハーブティーです。血行促進やデトックス効果も期待できます。ポットからゆっくり注いでお召し上がりください」
かおるさんが説明を添えて、透明のティーポットとカップを舞のテーブルに置いた。中には蜂蜜色の液体が入っている。そしてもう一つ、その隣に小さな器も。
「こちらはティータイムのお客様にサービスでお出ししている、蜂蜜入りオレンジのシャーベットです」
それを見て、舞はえっ、と目を見開いた。明るいオレンジ色のシャーベットに、小さなミントの葉が添えられている。
「あ、ありがとうございます」
舞はぎこちなく笑って言った。
ティーポットを傾けて、カップにゆっくりと注ぐ。そして、一口飲んでみる。熱すぎず、ぬるくもなく、飲むのにちょうどいい温度だった。
いい香り。それに、肩の力がすっと抜けていくようだ。
……問題は、シャーベットだった。
サービスというだけあって、皿の上にちょこんと乗っている小さなものだ。普通の人なら、きっと二、三口でぺろりと平らげてしまうのだろう。もともと痩せ体質で体型など気にもしていなかった瑠夏なら「ラッキー」なんて言って喜ぶかもしれない。
舞は、戸惑っていた。喜ぶどころか、嫌悪すら覚えた。でも、せっかく厚意で出してくれたものを残すのも躊躇われた。
舞は、これまで一度もアイスというものを食べたことがなかった。
『甘い上に冷たいなんて。あんなもの体に毒よ』
何度も母から聞かされるうちに、これは毒なのだ、と舞自身も思うようになった。味も感触もわからない。想像すらしたことがない。
でも、どうしてか、今なら自然とそうすることができた。この店の柔らかな雰囲気と、室内いっぱいに広がる花の香りのせいかもしれない。
――どんな味がするのだろう。
明るいオレンジ色のシャーベットが、太陽の光を浴びたようにキラキラと輝いて見えた。食べてほしいと言っているようだった。
シャーベットが少し溶けて、丸い形が崩れ始めている。
「どうかされましたか?」
気づくと、かおるさんが横に立っていた。
「いえ、なんでもないです」
舞は首を振って、思いきってスプーンですくった少量のシャーベットを口に運んだ。そして、目を見開いた。
――あれっ、思ったより甘くない。
蜂蜜が入っているならもっと甘さを感じると思ったのに、オレンジの酸っぱさとミントの爽やかな風味が際立っている。だけどそれだけじゃなくて、後からほのかな甘みも感じた。
「おいしい」
半分溶けかけているから、抵抗が薄くなったのかも。そう思うと、溶けかけのシャーベットも悪くないかもしれない。
シャーベットの後に温かいハーブティーを飲んで、冷たさを中和する。血糖値を抑えられる効果があるというから、罪悪感もそれほど覚えなかった。
ポットに残っていた残りの分も全部飲み干して恍惚に浸っていたとき、扉が開いた。
……えっ。何、あの人。
入ってきた若い男の人は、薄汚れた深緑色に同じ色の帽子――なぜか、軍服姿だった。どこもかしこも擦り切れて、ボロボロだ。
コスプレだろうか。だとしても、喫茶店に来るにはあまりに不釣り合いな格好だ。
彼は驚いたように店の中をきょろきょろと見回し、そしておばあさんのほうを見ると目を見開いて、
「――すみ子」
声を震わせながら、そう言った。
「まさしさん……!」
おばあさんの目から、ぼろぼろと涙がこぼれ落ちた。
――え? どういう状況……!?
窓際の席に座る舞は、はらはらしながらその様子を傍から見守る。
「どうぞ、そちらにおかけください」
と、かおるさんはとくに驚く様子もなく、にっこりとほほ笑みながら言う。
「えっ、ああ、失礼」
男の人は戸惑いながらそう言うと、慣れない手つきで椅子をひいて、おばあさんの向かいに腰を下ろした。
おばあさんと男の人の年齢は、見た目は親子どころか、孫ほども離れている。でも、不思議なことに、そうは見えなかった。
二人は、長い間遠く離れて暮らしていた恋人同士のようにはにかみながら、見つめ合っているのだ。
まさか道ならぬ恋とか? 嘘でしょ。この歳の差で?
「お待たせしました。コーディアルでございます」
かおるさんが見計らったように、グラスを二つ、テーブルに置いた。グラスには淡桃色のジュースのようなものが入っている。それからオレンジのシャーベットも。
「まあ、おいしそう」
おばあさんは涙を拭って、微笑んで言った。
コーヒーや紅茶に入れるならまだしも、シロップをそのまま飲むなんて。見ているだけでいかにも甘ったるそうなその液体を見て、舞はじわりと胸に不快なものが込み上げるのを感じた。
「ああ、甘くて冷たくて、とてもおいしいわ」
おばあさんは幸せそうに、頬を緩めてそう言った。
男の人は、物珍しそうにしげしげとカップを眺めてから、片手で持ち上げた。口をつけて、目を見開く。
「覚えてる? 昔一度だけ、白蜜をかけた氷を食べたの。あれがとってもおいしくて、忘れられなかったの」
「ああ、よく覚えている」
男の人は、懐かしそうに目を細めてうなずいた。
二十代半ばくらいかもしれないと思ったけれど、その表情は、少年のように幼く見えた。
二人とも、すごく楽しそう。向かい合って甘いお菓子を食べる子供のようにも、初めてデートをした恋人たちのようにも見えた。
不思議な光景だった。こんなにも歳が離れているのに、歳の差なんてどうでもよく思えてくる。二人の間には、そんなことは関係ないようだった。
しばらくして、男の人が立ち上がった。
「ずいぶんと時間がかかってしまったけれど」
男の人がおばあさんの隣に立って、膝まづいた。まるで、そこがスポットライトで照らされた舞台の真ん中のように。
「すみ子さん、僕と、結婚してください」
おばあさんが目に涙を溜めて、男の人を見上げた。
「ありがとう――嬉しいわ」
男の人は深々と頭を下げて、
「ありがとうございました」
そう言って再び上げた顔は、晴れ晴れとしていた。
おばあさんも立ち上がり、私も、と言いかけたのを、かおるさんが優しく手をとって引き止めた。
「名残惜しくても、一緒に行っては行けません」
と、またしても意味の分からないことを言う。
男の人が出て行ったあと、おばあさんが訥々と話し始めた。
「あの人とは幼馴染だったの。子供の頃からずっと一緒だったのに、気持ちを伝えられないまま戦争で離れ離れになってしまってね」
おばあさんは誰に言うでもなく、閉まった扉を見つめてそうつぶやいた。
「そうでしたか……」
かおるさんが目を真っ赤にしてうなずく。
「はい。このお店のことを話を風の噂で耳にしまして……最後に、来ることができて本当によかった」
おばあさんは言って、テーブルにかけていた杖を手に立ち上がった。
「そろそろ家族が心配するから行かないと。お姉さん、どうもありがとう」
「またいつでもいらしてください。おいしいハーブティーを用意してお待ちしています」
「ええ、きっとまた」
おばあさんは来たときと同じように、ゆっくりと扉を開けて出て行った。
舞はぽかんと口を開けて見送る。
「あの、さっきの男の人って……」
おそるおそる尋ねると、
「おそらく、戦時中にお亡くなりになったのでしょう」
かおるさんは潤んだ目をハンカチで押さえながら言った。
お亡くなりになった、と。
やっぱり――あの人は、生きている人ではなかった。
「それって……幽霊、ってことですか?」
でも、ハーブティーを飲んでいたし、足もあったし、あの人はちゃんとここにいたのに。
「ここは、あの世とこの世の通り道になっているみたいで、時々、こういうことが起こるんです。お互いが強く“会いたい”と願っているときだけ」
信じられないようなことが目の前で起こったのに、なぜか妙に腑に落ちた。
『ずっと会いたかった人に会えました』
あのラブレターのような不思議な文は、そういうことだったのだ。
「あの、さっき、一緒に行ってはいけないって言ってたのは……」
「ああ、あれは」
かおるさんが少し間を置いて、言った。
「扉が開いたときは、あっちの世界と繋がっているから。連れて行かれたら、もう二度と戻ってこられなくなるんです」
「え……」
ロマンチックな話が一気にホラーになった気がした。ということは、過去にそういうことがあったのだろうか。
きっとあのおばあさんは、何十年も、会えるのを待っていたのだろう。
ずっと、ではないかもしれない。違う人を好きになったこともあったかもしれない。
でもあの瞬間、お互いが強く“会いたい”と思っていたから、会えたのだ。
そんな奇跡が、目の前で起こったのだ。
「もし、相手が生きていても、会えることはあるんでしょうか」
舞は言った。
ここで待っていたら、会えるだろうか。
その人がどこにいるかわからなくても?
「わたしは昔、一度だけ、ここで生きている人に会ったことがあります。それがこのお店を始めるきっかけでした」
かおるさんは懐かしそうに目を細めて言った。
「ネリネという花を知っていますか?」
尋ねられて、舞は、いえ、と首を振った。
「冬の終わりから春にかけて咲くヒガンバナ科の花です」
「ヒガンバナですか」
前に祖母の墓参りに行ったとき、真っ赤な彼岸花が群れて咲いているのを見て、なんとなく不気味に感じたのを思い出した。
そういえば、この店の名前も『ネリネ』だった。
「ネリネの花言葉は、〝また会う日を楽しみに〟――再会を願う気持ちが込められているんです。喫茶店にさよならは似合いませんからね」
かおるさんは、優しい口調でそう言った。
会えるかもしれないし、会えないかもしれない。誰にもわからない。
でも、再会を願っている。
舞には、どうしても会いたい人がいた。
でも、その人は、自分に会いたいと思っていないかもしれない。
それどころか、もう二度と会いたくないと思っているかもしれない。
本当に会いたいのなら、瑠夏の実家や、昔通っていたバレエスクール、思い当たる場所はいくらでもあった。
でも、舞がそこへ足を向けることはなかった。
行きたくても、できなかったのだ。
瑠夏がいなくなった翌日、舞は、瑠夏の恋人を尋ねた。
彼は言いづらそうに、
『消えたいって言ってた。しばらく留守にするって』
と言った。
引き止める恋人を残して、瑠夏は本当にいなくなってしまった。
その言葉に、舞はショックを受けた。
たまに失敗して落ち込むことはあっても、瑠夏はすぐに立ち直って、後に引きずらない性格だった。
後ろ向きの言葉は、決して口にしなかった。
その瑠夏が、〝消えたい〟と言うなんて。
そして、瑠夏にそう思わせたのは、舞かもしれないのだった。
――瑠夏。
あの子はいったい、どこに行ってしまったのだろう。





 トップ
トップ